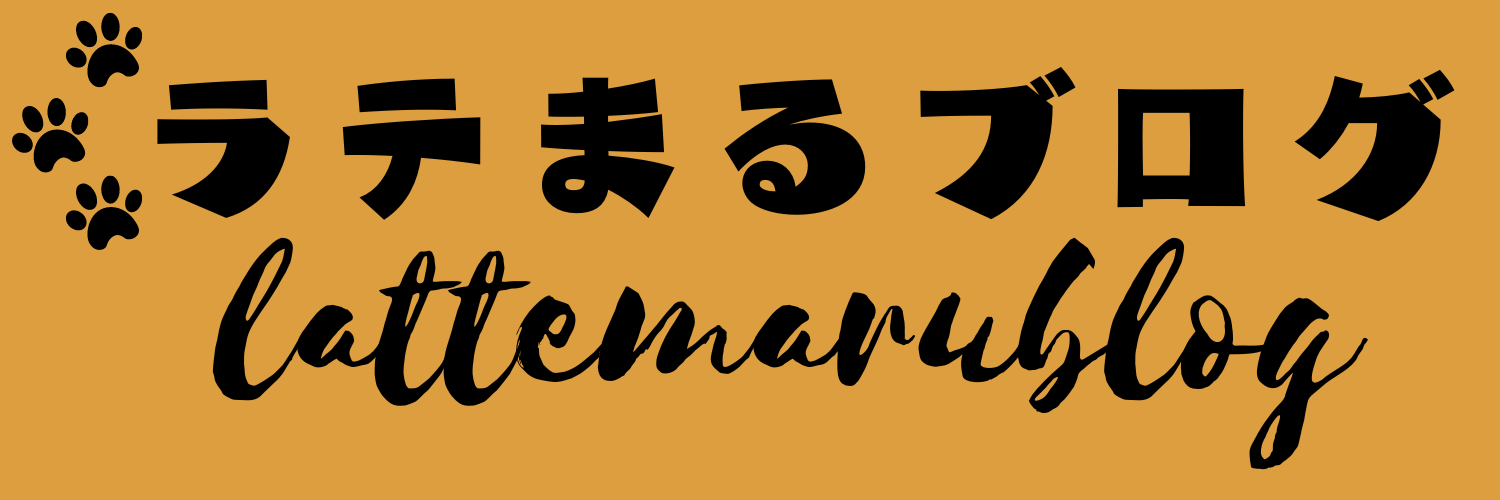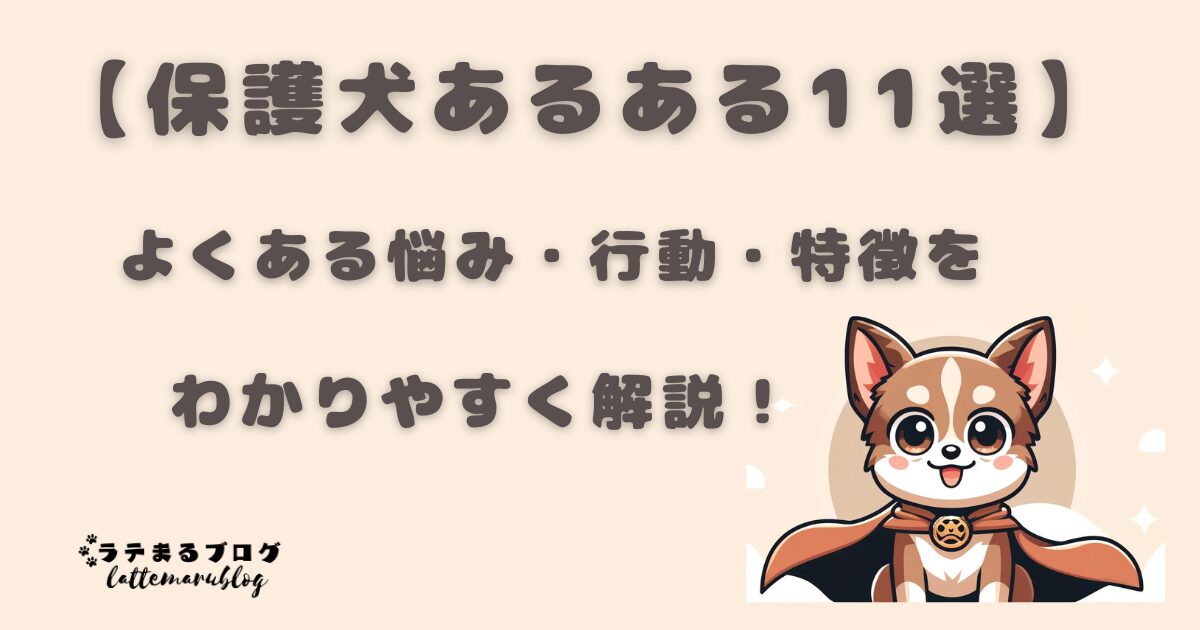飼い主ママ
飼い主ママ保護犬を迎えたけど、懐かない、散歩がこわい、留守番もうまくいかない…私、ちゃんとできてるのかな?
そんな不安やモヤモヤを抱えている保護犬の飼い主さんへ。



実はそれ、保護犬の「あるある」なんです!
小さな体に大きな過去を抱えてやってくる保護犬。警戒心が強かったり、散歩を怖がったり、思い通りにいかない姿に戸惑うのはあなただけではありません。
この記事では、私自身の体験をまじえながら、初心者さんでもすぐに取り入れられる「保護犬あるある11選」とその対処法を紹介します。
共働き家庭でも実践できる工夫や、子どもと一緒に楽しめる関わり方まで、具体的にまとめました。



記事を読めば「うちの子だけじゃなかったんだ」とホッとでき、様々な悩みが「小さな成功」へ変わっていきます。
未来には、安心して笑う家族と愛犬の姿があります。
きっとその一歩が、今日から始まります。
ぜひ最後まで読んで、一緒に心が通じ合う暮らしをつくっていきましょう。
保護犬あるある11選|よくある悩みと特徴をまとめて解説!


あるある①|警戒心が強くてなかなか懐かない



警戒心が強くてなかなか懐かないというのは、保護犬あるあるの中でも特に多く聞かれる特徴です。
保護犬は過去に強いストレスや恐怖体験をしていることが多く、それがトラウマとなって、「人は怖いもの」と認識していることがあります。



ラテまるも懐くまでに少し時間がかかりました。
特に最初のうちは、体をこわばらせたり、後ずさりしたり、逃げようとしたりすることがあります。
新しい環境や知らない人に対して、警戒して距離を置くのは、犬の防衛本能とも言えます。
この警戒心を少しずつ和らげるには、「無理に近づかない」「犬のペースで距離を縮める」「ゆっくり優しい声で話しかける」などの工夫が大事です。
焦らず、犬のタイミングを待つことが一番の近道です。
「信頼は一瞬ではなく、毎日の安心の積み重ねで生まれる」という気持ちで向き合ってみましょう。
保護犬が慣れるまでの期間については、こちらの記事で詳しく解説しています。
犬が後ずさりしたら、すぐ手を引かずに少し時間を置く、顔や体を近づけすぎないなどの配慮をすると良いでしょう。
また、おやつをそっと差し出すと、少しずつ自分から近づいてくることもあります。





あわてなくて大丈夫。ラテまるも最初はこわかったんだよ。
保護犬が懐かないと悩んでいる方は、こちらの記事もご覧ください。


あるある②|留守番が苦手で分離不安になりやすい



留守番が苦手で分離不安になりやすいというのも、保護犬あるあるのひとつです。
元繁殖犬や保護施設で過ごしてきた犬は、人と心を通わせる機会が少なく、愛情を十分に感じられないまま過ごしてきた子も少なくありません。
保護施設ではスタッフさんにお世話をしてもらう中で少しずつ安心を取り戻しますが、家庭の中での「温かいつながり」はこれから学んでいく段階です。
飼い主が出かけるときに吠えたり、家具を壊したり、トイレ以外で排泄をしたりするのは、まさに分離不安の典型的なサインです。
「留守番が苦手」「出かけると吠える」と悩む飼い主さんは多く、実はそれも保護犬の心のサインなんです。



チワワのような小型犬は、繊細で感情表現が豊かなため、この傾向が出やすいとも言われています。
分離不安については、こちらの記事で詳しく解説しています。
ラテまるも最初のころは、私が出かけるたびに落ち着かなくなってしまい、帰宅するとクンクン鳴いていました。
でも、「姿が見えなくても安心できる環境」を少しずつ整えることで、今では「いってらっしゃい」と言うように静かに見送ってくれるようになりました。
留守番が不安な子のためには、以下のような工夫が効果的です。
- 出かける時間を徐々に延ばす「ステップ練習」をする
- おもちゃや知育トイで気を紛らわせる
- 慣れた寝床やお気に入りの毛布を用意して安心できる空間をつくる
- 外出中も声や姿を感じられるように、見守りカメラを活用する
- どうしても不安が強い場合は、ペットシッターに短時間から頼んでみる
特に我が家では、「Furbo(ファーボ)ドッグカメラ」が大活躍でした。
外出先からラテまるの様子を見守れたり、声をかけたりできるだけで、お互いの安心感がぐっと増しました。


実際に使ってみたファーボの口コミとレビューは、こちらの記事をご覧ください
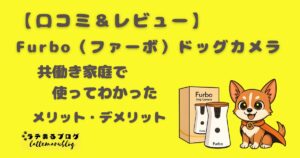
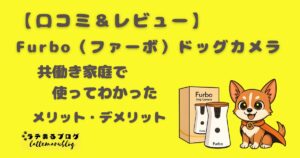
また、出張や長時間の外出が多いご家庭では、「ペットシッターサービス」を利用するのも一つの方法です。
自宅に来てもらえるタイプなら、犬にとっても慣れた環境でお世話を受けられるため、ストレスを減らすことができます。
飼い主が外出中でも、安心して過ごせるサポートとして検討してみるのもおすすめです。





ラテまるも今では、毛布の上で「いってらっしゃい」の顔をしてくれるよ。少しずつ信頼関係ができてきたんだ。
あるある③|環境の変化で体調を崩しやすい



引っ越し、生活リズムの変化、家族の動きが変わるなどがストレスになり、下痢・嘔吐・食欲低下・元気がなくなる、という症状が出ることがあります。
犬はストレスを感じやすく、それが体の免疫や消化器に影響を及ぼすからです。



特に高齢の犬やチワワのような小型犬だと、消化器系や体力の変化が起こりやすいため、この点は気をつけたいですね。
特に「下痢をする」「環境が変わって食べない」といった悩みを持つ飼い主さんは多く、それは新しい暮らしに慣れるための一時的なサインであることもあります。
あまりにも体調が優れない場合には、獣医師に相談し、検査を受けることが重要です。
日常的には、
- 食事を変えるときはゆるやかに切り替える
- 新しい部屋に慣れる時間をとる
- 安心できる寝床を準備する
- 急な温度変化に気をつける





ラテまるも最初の数日、おなかがゆるくなったことがあったよ。でも、おだやかな環境で落ち着いたら良くなったんだ。
あるある④|脱走や隙間からの逃げ出しに注意が必要



保護犬の脱走や隙間からの逃げ出しは、飼い主が特に気をつけたい「あるある」です。
警戒心が強く、怖いものから逃げ出したい気持ちが働くと、フェンスやドアの隙間を抜けようとすることがあります。
また、音や人の気配に敏感な子は「知らない場所に行って隠れたい」という気持ちが強くなることもあります。
新しい環境では、自分の「安全地帯」がまだ見つけられず、不安で動き回ってしまうケースも多いです。
脱走が起こりやすい場所としては、玄関や庭まわり、門扉、勝手口、網戸などが代表的です。
少しのすき間でも小型犬はすり抜けてしまうことがあるので、日常的な点検が大切です。
保護犬が脱走してしまう原因の多くは「不安」と「環境の変化」です。
チワワなどの小型犬は、ちょっとした音やドアの開閉にも反応してしまうことがあります。
脱走対策としては、以下のような方法が有効です。
- フェンスや門扉のすき間をなくす(結束バンドやネットで補強)
- 玄関の前には見通しのいいスペースをつくらない
- リードをつけて外に出すときは必ず「ダブルリード」にする
- マイクロチップや首輪タグを必ず装着しておく



我が家では、リビングの出口に脱走防止柵を設置しました。


最初は少し見た目が気になりましたが、設置してみると安心感がまったく違います。
小さな対策でも「守ってあげている」という気持ちが、自分たちにも伝わってきます。



ラテまるも一度だけ玄関にダッシュしそうになったけど、柵があってセーフ!
今ではちゃんと「待て」ができるようになったんだ♪
保護犬を迎えるときは、脱走防止グッズだけでなく、安心して過ごせる環境づくりも大切です。
初めての方は、どんなアイテムを揃えればいいのか迷うかもしれませんね。
そんな方に向けて、こちらの記事でわかりやすく紹介しています。
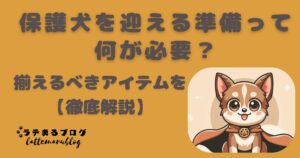
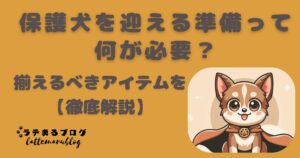
あるある⑤|散歩を怖がる子も多い



ラテまるも最初は震えて散歩を嫌がっていました。
チワワは小型で繊細な体をしているため、車の音や風の音、地面の振動、人の足音などに敏感に反応する子が多いです。
保護犬の場合、外の世界に慣れていないため、ちょっとした刺激でも不安になってしまうことがあります。
最初の頃は、リードをつけただけで固まったり、一歩も動けなかったりすることも珍しくありません。



「外に出ると怖がって歩かない」「すぐ座り込んで動かなくなる」
そんなお悩みを抱える飼い主さんはとても多いです。
怖がる理由としては、外の刺激に慣れていないこと、過去に怖い経験をしたこと、もしくは筋力が落ちていて歩くことに不安を感じているなどが考えられます。
でも、散歩は「運動」だけでなく「気分転換」や「社会化」のためにもとても大切です。
怖がりな子でも、無理をせず少しずつ慣らしていくことで、外の世界を楽しめるようになります。
チワワの散歩はどれくらい必要?時間や距離の目安はこちらで解説しています。
怖がりな保護犬にとって大切なのは、「外は怖くない場所」だと感じてもらうことです。
そのためには、まずは室内や玄関先でリードをつけてみるなど、小さな成功体験を積み重ねることがポイントになります。
- 室内でリードをつける練習をする
- ベランダや玄関先で少しだけ外気を感じさせる
- 短時間の散歩から始める
- 褒める・おやつをあげるなど「楽しい経験」に変える





最初は玄関を出るだけでドキドキだったけど、少しずつ慣れて「お散歩=楽しい」って思えるようになったよ!
散歩で歩かないとお悩みの方は、こちらの記事も参考にしてください。


あるある⑥|トイレの失敗や粗相が多い



トイレの失敗や粗相が多いことも、保護犬あるあるです。
「何度教えてもトイレを失敗してしまう…」「粗相を見るたびに落ち込んでしまう…」
そんな悩みを抱える飼い主さんは本当に多いんです。
特に新しい家に来た直後は、トイレの場所がわからなかったり、怖くて外でしてしまったりすることがあります。
また「留守番中だけ粗相する」というケースは、分離不安が影響している可能性もあります。



失敗の要因としては、以下がよく挙げられます。
- トイレの場所が定まっていない
- 寝床とトイレが近すぎる(犬は寝床近くで排泄するのを避けます)
- 叱ってしまって怖くなった
- 体調不良や排泄間隔が合っていない



では、よくある失敗への対策例を見ていきましょう。
- トイレと寝床をできるだけ離して設置する
- 成功したらすぐ褒める
- 失敗しても叱らず、そっと片付ける
- 留守番時はサークルなどで制限空間を用意する





ラテまるは、最初からトイレは上手にできたけど、安心できる環境を作るまではソワソワしてたよ。
トイレトレーニングのコツについては、こちらの記事も参考になります。


あるある⑦|吠えない・声を出さない犬もいる



吠えない・声を出さない犬もいるという特徴も、実はよくある保護犬あるあるです。
「全然吠えないけど、大丈夫なのかな…?」
そんな心配をする飼い主さんは少なくありません。
一般的には「吠える犬のしつけ」が注目されがちですが、実は「吠えないこと」にも理由があります。
過去に吠えることを叱られ続けた、声帯を切られていた、あるいは極度の警戒心から声を出せない。
こうした背景を持つ保護犬は、吠えることそのものに恐怖を感じてしまう場合があります。
ただし、吠えないことが悪いわけではありません。
無理に声を出させるのではなく、犬が安心して「気持ちを表現できる」環境を整えてあげることが大切です。
そのためには、穏やかな声かけ・スキンシップ・安心できる居場所づくりがポイントです。



ラテまるは繁殖引退犬として保護され、声帯を切られていました。
そのため大きな声では吠えられませんが、お迎えしてから少しずつ小さな声が出せるようになってきました。


最初は無音で口を動かすだけでしたが、今では「ごはん」「おかえり」と言葉をかけると、小さく「ワン」と返してくれるようになりました。
その変化が、家族にとって何よりうれしい成長です。



昔は声を出すのがこわかったけど、今は安心して「ワン」って言えるようになったんだ♪
ラテまるのように「吠えない保護犬」が声を取り戻すまでの道のりや、安心して過ごせる工夫については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
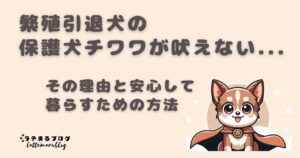
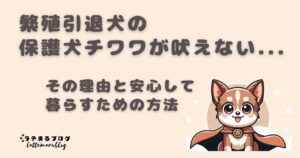
あるある⑧|要求吠えや夜鳴きが強く出る子もいる



逆に要求吠えや夜鳴きが強く出る子もいるという極端なパターンも、保護犬あるあるです。
留守番中、夜中、あるいは飼い主がそばにいるときに「構ってほしい」「寂しい」「不安」などの感情から吠えることがあります。
これは「分離不安」「ストレス」「コミュニケーションの不足」が原因になることが多いです。
特に共働きで日中留守にする家庭では、この要求吠えが発生しやすく、子どもが驚いたり周囲への配慮に困ったりすることもあるでしょう。



対策としては、
- 飼い主がいる時間を少しずつ増やす
- 夜は寝る前に軽い運動をさせる
- 落ち着ける場所をつくる
- 無視する、構いすぎないなどの対応を適切にする
- 必要なら専門家のサポートを受ける
保護犬との生活では、仕事や家事との両立に悩む飼い主さんも多いですよね。
「長時間のお留守番で寂しい思いをさせていないかな…」と感じることもあると思います。
そんな共働き家庭でも、ちょっとした工夫で保護犬が安心して過ごせる環境を整えることができます。
詳しい留守番対策や環境づくりの工夫については、こちらの記事で紹介しています。





夜、さみしくて吠えちゃったこともあったけど、少しずつ夜も平気になったよ。
あるある⑨|食が細い、ご飯を食べないことがある



食が細い、ご飯を食べないことがあるのも、保護犬ではよく見られる「あるある」です。
新しい環境やフードに慣れず、緊張やストレスで食欲が落ちるのは珍しいことではありません。
特にチワワのような小型犬やシニア犬は、体調や歯の状態、消化力などの影響を受けやすい傾向があります。
ラテまるもお迎えしてから2日間はほとんど何も食べず、3日目になってようやく少し口にしてくれました。
保護犬がごはんを食べないときの対処法は、ラテまるの実体験をもとにしたこちらの記事で詳しく紹介しています。
実はラテまるは繁殖引退犬で、お迎えした時にはすでに歯がすべてありませんでした。


少しずつ食欲も戻り、笑顔を見せてくれるようになりました。
そのため、固いドライフードは食べられず、柔らかいウェットフードやふやかしたごはんに切り替える必要がありました。
歯がない犬の食事選びについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。



最初はとても心配でしたが、安心できる環境と食べやすいごはんを整えてあげることで、少しずつ食欲が戻っていきました。
ドライフードを食べない場合は、次のような工夫を試してみましょう。
- フードをぬるま湯でふやかして香りを立たせる
- ウェットフードを少し混ぜて食べやすくする
- 1回量を減らして、1日2〜3回に分けて与える
- 静かで落ち着ける場所で食事をさせる
- 食べない期間が長い場合は、早めに動物病院で相談する
また、ドライフードとウェットフードの違いを知っておくと、愛犬に合った食事を選びやすくなります。
それぞれのメリット・デメリットを比較したこちらの記事も参考になります。





ラテまるは歯がなかったから、ドライフードは食べられなかったの。やわらかいごはんに変えてから、少しずつ食べられるようになったんだ♪
ラテまるが食べているウェットフードの比較記事はこちらをご覧ください。
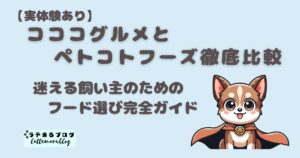
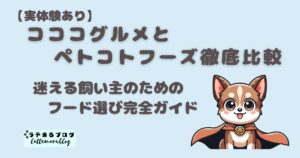
あるある⑩|体に触られるのを嫌がる子も多い



過去に虐待や無理な扱いを受けた経験があると、触られること自体が恐怖のトリガーになることがあります。
爪切り、耳掃除、ブラッシング、抱っこなど、日常ケアの際に強く抵抗することがあるでしょう。
このような場合は、無理に触らず、「触られることは安全だ」という体験を少しずつ積むことが重要です。
短時間だけ手を近づけて褒める、撫でられる時間を少しずつ延ばす、触られたらご褒美をあげるなどのステップを踏む方法が有効です。
時間はかかるかもしれませんが、根気よく慣れさせることが信頼関係を育む鍵です。


今では安心しきった表情でへそ天ポーズを見せてくれるようになりました。



最初はお腹を撫でられるのがイヤだったけど、今はだいすきなんだ。
少しずつ安心して暮らせるようになると、保護犬もリラックスした姿を見せてくれるようになります。
ラテまるも今では、お腹を見せて仰向けで寝る「へそ天ポーズ」をするようになりました。


犬がへそ天で寝るときの心理や性格の特徴については、こちらの記事で詳しく解説しています。


あるある⑪|他の犬や人との関わりに慣れていない



他の犬や人との関わりに慣れていないというのも、保護犬によく見られる特徴です。
保護犬は、幼いころに十分な社会化経験を積めなかったり、過去の怖い体験から人や犬に不安を感じやすい傾向があります。



そもそも「保護犬」って、どんな経緯で保護される犬のことを指すのか気になりますよね。
ラテまるも元は繁殖引退犬として保護された子です。
保護犬にはそれぞれの過去があり、その背景を知ることで接し方や理解の仕方も変わってきます。
保護犬の定義や保護される理由については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
繁殖犬とは、ペットショップなどに子犬を供給するために繁殖を繰り返してきた犬のことです。
中には、長い間ケージの中で過ごし、人との触れ合いがほとんどなかった子もいます。
繁殖犬の実態や、保護される背景については、こちらの記事で詳しく解説しています。
こうした背景から、初対面の犬や人に対して怖がったり逃げたり、時には威嚇してしまうこともあります。
無理に接触させず、少しずつ「大丈夫」と思える経験を積ませてあげましょう。
他の犬とすれ違う練習を短時間から始めたり、人が近くにいても落ち着けるスペースを作るなど、段階的に慣らしていくのがおすすめです。
焦らず、愛犬のペースで「信頼できる世界」を広げてあげることが大切です。


少しずつ慣れていく姿に成長を感じました。



ラテまるも最初は他の犬がこわかったけど、だんだんお友だちになれたんだよ。
保護犬あるあるを前向きに楽しむ工夫


子どもと一緒にできる保護犬とのふれあい方



保護犬とのふれあいは、子どもにとっても大きな学びになります。
まず、子どもには「急に触らない」「大きな声を出さない」「犬の目線でゆっくり近づく」などのルールを教えてあげましょう。
犬のペースを尊重しつつ、子どもがそっと近づいて撫でる、優しく話しかけるといった体験は、犬に安心感を与えます。



子どもと一緒にブラッシング、軽いマッサージ、散歩の補助などを家族で役割分担すると、犬との時間が自然に増えます。
「今日はお兄ちゃんがリードを持つ」「妹がおやつをあげる」など、役割を与えることで子どもも参加しやすくなります。
こうした経験を通じて、子どもは「生きものを大切にする心」「相手への配慮」「命の尊さ」などを学ぶことができます。
保護犬との生活は、家族の絆を育む機会にもなるのです。


子どもたちとの時間が、少しずつ大好きになっていきました。



子どもたちと遊ぶのがだんだん好きになったよ。
成長や変化を家族みんなで共有する喜び



保護犬と暮らすと、小さな変化が日々起こります。
「保護犬って、どんなふうに心を開いてくれるんだろう?」そんな気持ちで日々を見守る時間も、家族にとって大切な宝物です。
初日は警戒していたけれど、「お座り」ができるようになった、抱っこを許すようになった、散歩で尻尾を振るようになった…



そんな成長を家族みんなで感じる喜びは格別です。
日記のように変化を記録しておくと、後で振り返ったときに「こんなに成長したんだ!」と実感できます。
子どもが「この前は触れなかったけど、今日は撫でられたね」と気づいたとき。
そんな小さな変化を家族みんなで喜び合うことで、保護犬との絆もぐっと深まります。
その瞬間を写真や動画に残しておくと、あとで見返したときに「ここまで成長したんだね」と感じられて、胸がじんわり温かくなるものです。





みんなが優しく見守ってくれたから、少しずつ変われたんだ♪
保護犬との生活で学べる思いやりと忍耐



保護犬との暮らしは、思いやりと忍耐を育てる日々です。
「どうしてこんなに怖がるんだろう…」と悩む日もありますが、そんな時間も大切な信頼づくりの一歩です。
犬が怖がるとき、すぐ反応するのではなく、まず心を読もうとする配慮。
犬が失敗しても叱らずに見守る忍耐。
こうした姿勢は、子どもたちや家族にも伝播します。
「命を迎えるとは、こんなにも慎重な心遣いが必要なんだ」と日々感じることで、家族全体の優しさが育まれます。



逃げ出したい気持ちを抱える犬を少しずつ受け入れる経験は、人間関係にも通じる学びになることがあります。
「待つ」「信じる」「見守る」ことの価値を、犬との暮らしを通じて実感できるのは、保護犬ならではの醍醐味です。



優しくしてくれた時間が、信頼に変わったんだよ。
保護犬を飼うための覚悟については、こちらで詳しく解説しています。
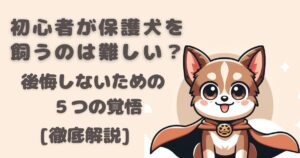
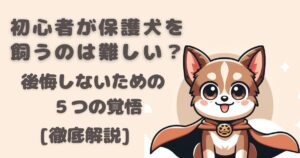
保護犬だからこそ感じられる絆の深まり



保護犬だからこそ、普通の犬よりも絆が深くなる瞬間がある。
それは何よりの魅力です。
最初は距離があったけれど、一緒に暮らしていくうちに体を寄せてくる、尻尾を振る、目を合わせる、甘える…。そんな瞬間は心に強く残ります。



「この子を迎えてよかった」「命を救えて本当によかった」と感じるたびに、家族としての絆が深まっていくのを実感します。
日常のささいな触れ合い、夜の安心した寝顔、散歩中の一歩。
こうした小さな瞬間を大切に重ねていくことで、絆はゆっくり、でも確実に育っていきます。


信頼と愛情がゆっくりと育まれていきました。



この家族の一員になれて、本当によかった。
「いつか保護犬を迎えてみたい」と思った方は、こちらの記事で最初の一歩をチェックしてみてください。


保護犬の悩みを相談できるQ&Aサービスも活用してみよう!



保護犬との暮らしを前向きに楽しむためには、「悩みをひとりで抱え込まないこと」も大切です。
保護犬を迎えたばかりの頃は、食事・しつけ・体調・夜鳴きなど、不安や疑問がたくさん出てくるものです。
そんなときに心強い味方になってくれるのが、無料のペットQ&Aコミュニティサービス「DOQAT(ドキャット)」です。
犬や猫を飼っている飼い主さん同士が、日常の悩みを投稿したり、回答したりできるコミュニティで、同じ犬種や環境に近い人の体験談を読めるのが魅力です。



チワワの分離不安・トイレトレーニング・夜鳴きなど、ラテまるのようなケースに近い質問も多く、リアルなアドバイスが見つかることがあります。
また、すべての回答が獣医師監修ではありませんが、投稿の中には「専門家のお墨付き」ラベルが付与されることもあり、信頼性が高い点も安心です。
登録は無料で、会員になるだけで週に1回、あなたの愛犬に似た質問と回答がメールで届く便利な機能もあります。



困ったときに相談できる場所があるって、ほんとうに心強いね!
悩みを抱え込まずに、同じように保護犬と暮らす仲間の声を聞くことで、「うちだけじゃないんだ」と気持ちが軽くなるはずです。
DOQATの使い方や評判、実際に使ってみたレビューは、こちらの記事で詳しく紹介しています。


まとめ|保護犬あるあるは家族の絆を深める第一歩



保護犬あるあるには悩みもありますが、理解して寄り添うことで、少しずつ信頼と笑顔が戻ってきます。
「吠えない子」「トイレが苦手な子」「怖がりな子」、どんな子にも、その子なりの理由と背景があります。
焦らず見守り、小さな変化を家族で喜び合うことが、絆を深める第一歩です。
保護犬との暮らしは、簡単ではないけれど、かけがえのない幸せに満ちています。
困ったときは一人で抱え込まず、仲間や家族、同じように頑張る飼い主さんたちと支え合いながら歩んでいきましょう。



これからも、ひとつひとつの「あるある」を笑顔に変えていこうね🐾